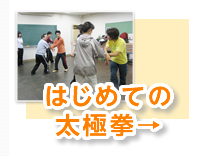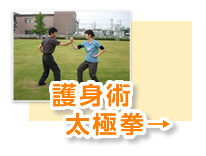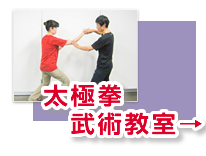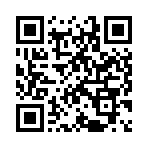2018年04月11日
骨盤をたわめる~細くなる身体
私の行っている双辺太極拳は身体をかなり細く薄く使います。
足を前後に開いて立った時、前後の足の幅は線が1本。つまりほぼゼロです。
一見バランスが悪いようですが、踏ん張って止まって打ち合う事はなく
動き続けることが前提ですから良いのです。
細く立つことで、重心移動と体の移動がぶれることなく行え、移動の速さが上がります。
また、打撃に重心を乗せやすくなります。
更に、相手にさらす正面の身体面積を狭くできます。これは対武器の際に大切です。
しかし、これには、骨盤を縦に動かす(といっても横長の長楕円です)という動きや、
骨盤を閉めるようなやや難しい動きが必要とされます。
左足前で、右拳を打ち込む時、骨盤の左上前腸骨棘(腰の横でベルトの引っかかる出っ張り)
を動かないようにして、右の上前腸骨棘をたわめるように前に出していきます。
最終的には左右の上前腸骨棘が揃って、おへそが正面を向きます。
そして、正面から見た身体が通常の状態よりも、やや細くなります。
これは右上前腸骨棘を前に出す際に、骨盤をたわめるようにしたためです。
ちょうど下敷きをたわめて、半円を作るようなものです。一見難しいようですが、
段階を追って適切な訓練を積めば、誰にでも可能な身体操作です。
こうした身体操作で身体の中の力を手や肘に集めて、そこから相手に大きな力を
打ち込むことが出来ます。
簡単なチェックとしては、誰かに前に立ってもらい、足を前後左右に開いて
動かされないように頑張ってもらう、というものがあります。
そうした相手の左右の胸に両掌を軽く当てて、骨盤をたわめつつ
身体全体で押していきます。くれぐれも力んで局所に力を込めてはいけません。
双按の要領です。
上手く力を集めることが出来れば、自分では力を出している感覚が無いまま
相手を軽く崩すことが出来ます。場合によっては、相手が吹っ飛んでいきます。
一種の掤勁・発勁です。
こうした身体をたわめる操作は、もちろん骨盤に限ったことではありませんが、
それは、またの話。
2018年03月01日
骨盤を動かす
よく骨盤が開いている、などと言います。しかし、「骨盤というのは
蝶々のようになっていて、蝶々の羽の部分が開いたり閉じたり」という
訳ではありません。骨盤は一種の筒状になっています。後ろは寛骨と仙骨
前は左右の恥骨が結び付いて、一種の環を構成しています。
ですから、骨盤はほとんど動かないのですが、
仙腸関節で微妙に動いているわけです。
特に女性は周期的に動きますし、妊娠すれば必然的開いていきます。
妊娠中に骨盤が開いていくのが分かった、という女性もいました。
武術でも、微妙に骨盤を動かします。
正中面を境にして、右半身と左半身を別々に動かしていく身体操作があります。
骨格から見れば、そんな事は簡単には出来ないのですが、骨盤を上手くたわめて
使うことによって、左右の半身を別々に扱う事が可能になります。
これは、そのような操作をする事で、ある技が技として成立するかしないか、
という程の違いがあります。
太極拳のゆっくりした動きならではの稽古の結果、そうした一般的ではない
身体操作が可能になります。
2015年02月05日
知っておくと便利な太極拳の解剖学…骨盤
骨盤は左右の寛骨(腸骨・坐骨・恥骨で構成される)と仙骨・尾骨で出来ています。
左右の腰に手を当てると腸骨の上縁(腸骨稜)に当たります。腸骨稜に沿って掌を前に移動させると、腸骨の前面の突起に当たります。これが上前腸骨棘です。これは丁度ズボンの横のポケットに半分くらい手を入れると当たります。骨のでっぱりのような感じなので、ほとんどの人で分かると思います。
この骨盤の前のでっぱり(上前腸骨棘)は太極拳の腰の動きを見る良い指標になりますので、覚えておくと便利です。
骨盤の上縁を後ろにたどっていくと、上後腸骨棘という小さなでっぱりがあります。後ろのでっぱりは、前のでっぱり(上前腸骨棘)ほどはっきりしていません。この骨盤の後ろのでっぱりの内側に仙骨があります。ですから、この後ろのでっぱりの内側が 仙腸関節 です。
さて、これで主な キーワードが揃いました。
骨盤の前のでっぱり(上前腸骨棘)
骨盤の後ろのでっぱり(上後腸骨棘)
仙腸関節
それと、椅子の座る時に、座面に当たる左右のお尻の骨のでっぱりが坐骨結節です。
上半身では肩甲骨を意識して腕を動かすと動きが良くなります。手の動きは肩甲骨から力が流れるようにします。そして、肩甲骨と骨盤は連動します。
太極拳では、腰を引いたり進めたりしつつ、体重移動を伴って技を行います。腰の動かし方は流派によって違いますが、内家拳ではそれ程の違いはありません。まず、腰は水平には回さずに、縦に動かす感覚です。身体を縦に分割して、①背骨②右半身③左半身 と意識して動かします。ですから、例えば右半身を後ろに引いた時に、右の腰を回して左半身の領域に入ってはいけないわけです。
ここで、先ほど話した仙腸関節や坐骨結節が出てきます。例えば、右半身の後ろへの体重移動は、右の坐骨結節が右の踵の上に来るようにします。この時、仙腸関節を境に、右寛骨が真後ろに下がります。寛骨の動きが左右にぶれてはいけません。体重を前に移動して突いたりするときには、骨盤をたわめるようにして左右の寛骨を前に進めるようにします。イメージとしては下敷きをたわめる感じです。この時もやはり、左右の寛骨を仙腸関節で分離して1つ1つを独立させて動かす感覚が必要です。手を動かすような感覚で、寛骨や仙骨を動かす事が出来れば、動きの質が変わってきます。
緩めた仙骨の威力 : 站椿の要領で立ちます。その時、特に左右の仙腸関節を意識します。そして仙腸関節周囲の筋を緩めます。うまく筋肉が緩まない時には、わざと少し力を入れて抜く、入れて抜く、を繰り返してください。そうして仙骨周囲が柔らかくなり、仙骨が独立して存在している感じになります。これで準備が出来ました。左右の手首を誰かに握って動かないようにしてもらいます。そうしたら、自分は、ゆっくりと仙骨のリラックスした感じを味わいつつ掴まれた両手を目の前に挙げていきます。
仙骨の周囲が緩んでいると、相手が強い力で握ってきても、軽く腕を上げる事が出来ます。仙骨の状態を変えていくつかのバージョンで試してみてください。得るものが多いと思います。