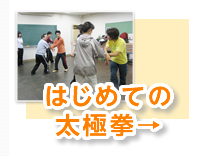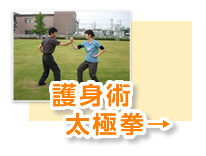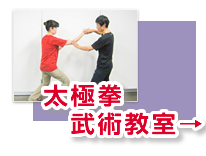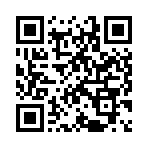2022年10月09日
バランス感覚と正中線
諸般の事情でバランス感覚が低下している60代男性Sさん。
太極拳では蹴りの動作以外にも片足に全体重をかける動きが
頻繁に出てきます。そこで色々と細かい注意をして練習してもらいました。
まず足の裏の重心を把握する。
拇趾の付け根、小趾の付け根、踵、の3点にしっかり荷重する。
その上で踵よりもつま先側にやや多く荷重する。
更に、小趾よりも拇趾側に少し多めに荷重する。
足裏の3点に十分に荷重した上で、拇趾に少し多めに荷重するという
事になります。これは太極拳の型稽古だけでは習得に時間がかかるので
站椿や気功のような足の動きがない練習で意識的に稽古してもらいました。
太極拳の型稽古で片足に全体重をかける時。
この時には、拇趾の付け根辺りから垂直に棒が立っていると想定して、
その棒の位置に頭を持って行くようにします。バランス感覚のいい方は
自然に行っている事ですが、それを「明確な意識」を持って行う事が
肝要です。
それを続けていると、正中線の感覚がだんだんはっきり自覚出来てきます。
具体的な視覚イメージを提示する事で、それが現実に作用するものとなります。
正中線や軸については、観念的なものや妄想にしかなっていない方もいます。
太極拳では、意念の力を実用的な道具に変換できなくてはなりません。
バランス感覚が悪いがゆえに努力をしたことで、上手く正中線の把握が出来ました。
2019年05月22日
足裏の重心位置・注意すべき3点
踵については、私の習った先生はとても厳しい方でした。
太極拳の型稽古の時に、初心者は後ろ足の踵が動きがちです。
すると、「ちょろちょろ踵を動かすんじゃねぇ!」
と怒鳴ったものです。定歩で重心の前方移動・後方移動が
繰り返される型では、油断をしていると
つい足が動いてしまします。
足の裏の意識は、拇趾の付け根・小趾の付け根・踵
の3か所にあって、その3点をしっかり地面につけます。
その条件で、さらに拇趾の付け根に他の2点より多くの重心を
かけるようにします。
それには、足背・下腿・大腿の纏絲勁が関係してきます。
なので、初心のうちは、重心を多めに、拇趾の付け根に
落とす、という感覚を磨くことです。
拇趾の付け根に重心を落とすことと、踵を動かさない、ということは
どうも、稽古量の少ない方にとっては、両立が難しいようです。
拇趾に意識が行くと、つい踵が浮き加減になります。
踵を意識すると、拇趾に重心がかからなくなります。
踵については、よく陳式の方が、踵重心を強調されています。
また、「五輪の書」でも「踵を強く踏む」という記載があります。
その時に拇趾については、どうなっているのかというと、
どの指とはありませんが、つま先を少し上げるという記述があります。
陳式ではどのようにしているか、知りませんので
陳式が専門の方が、この記事をご覧になったら、
ぜひともご教授お願いします。
足裏の1点のみ取り上げて比べることは出来ません。
全身を含めてトータルで所定の効果が出るような工夫がされているはずです。
興味深いことです。
そういうことで、はっきりと目に見えない足の裏でも
色々と鍛錬がされています。
最初のうちは目に見えないのですが、日々の稽古の成果が出てくると、
足の甲の筋肉がよく動くようになります。
目で見て分かるほどに、足の甲の幅が狭くできたりしますので、
確認の指標になります。
2017年06月29日
膝の位置と足裏の重心
流派により違いはありますが、多くの場合、
足裏の重心位置は母趾の付け根にかけています。
私の習った太極拳では、足の裏全体をベッタッと床につけて
その上で、さらに母趾の付け根に重心を置くようにします。
重心を足裏の適切な位置に置く為には、
いくつかの要素があります。
まず足の小指側を持ち上げるようにして重心の位置を
母趾付け根に行くようにする事。もちろん、実際に小指側が
持ち上がることはありません。熟達すると、足の甲の骨
(中足骨)が寄るように動くので分かります。
そして、脛の横にある腓骨筋という筋肉が良く働くように
なってきます。腓骨筋を意識的に動かすことが出来るようになれば
かなり上達してきたといえます。
もう1つの要素は膝の位置です。
流派や型の動きによって違いがありますが、
足裏の重心が安定する膝の位置というのがあります。
これは、先生の教えをしっかり理解して、
先生の動きをコピーできるように工夫することが大切です。
服の上からだと、膝の動きが分かりにくいこともありますので、
可能ならば、先生のズボンを上げて頂いて、膝の動きを
観ると参考になります。
私が初心者の頃、先生が拳法着に着替える時間がなく、
平服で稽古に来たことがありました。
その時に先生は
「今日は膝の動きが良く観えて良いな」
と言っていました。
だぶだぶの拳法着よりは、細めのスラックスは
確かに膝お動きが分かりやすいものです。
合気道の塩田先生も、植芝先生の膝の動きが袴なので
分かりにくかった、という事を書いていました。
膝の位置は大切ですね。