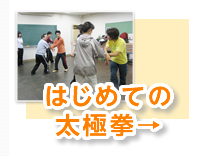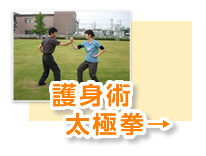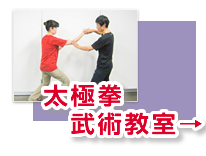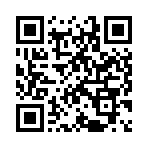2016年05月24日
太極拳と足の裏②
足の裏はべったと全体が床に着きます。
踵・足の小指の付根・母趾の付根の全てが
床に着くようにします。
その条件で、拇指の付根に重心を集めます。
中足骨(足の甲にある長い骨)が寄ってきて
足の甲が少し細くなるように感じられます。
その時に、気をつけないと小指側が床から
離れたり、足趾に変な力を入れすぎて
足趾の付根が浮いてしまいます。
最初は見る目のある人に確認してもらわないと
足裏の重心がどこにかかっているか、意外に
分からないものです。
上手く足裏の状態が出来ると、無理に力を
入れずとも、爪先から踵まで、
全体で床を掴んでいる感じが出てきます。
拇指は僅かに外反母趾のような感じになります。
側背部は中足骨がまとまってきます。
注意点は、無理に足趾で床を掴もうとしない事です。
足裏と足背部の適切な緊張状態が出来れば、
不用な力が無くなり、一種のリラックスした状態に
なってきます。そして重心の落ちてくる感じの準備が
整います。
うまく出来ているか分かりやすい指標は、脛の外側にある筋肉、
長腓骨筋・短腓骨筋がしっかり働いているか否かです。
母趾の付根に重心を落として、その状態で足の外側、小指から踵までを
上げようとします。しかし、そこにはアロンアルファーが付いていて
足の外側は床に着いたままです。・・・・・という状態にするのが
長短腓骨神筋です。
慣れないと、そうした操作を、膝を内側に入れる事で
やろうとします。しかし練習してくると、だんだん長短腓骨筋が
働くようになってきます。
Posted by 渡辺克敬(わたなべ かつゆき) at 23:22│Comments(0)
│太極拳、武術関連の話題