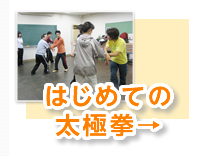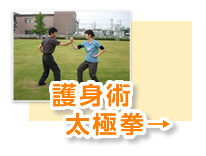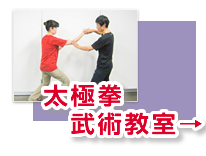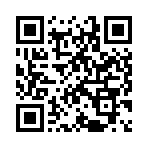2015年05月22日
太極拳と足の裏2
足の裏からさらに地面に重心を落として、身体を重く使う。これは、技が決まった一瞬の事です。太極拳で良く言われる 「含胸抜背」 や 「意守丹田」も そうですが、型の時に常に行っている事と、技を使う時に一瞬行う事の使い分けが必要です。足裏の重心感覚や含胸抜背は最初のうちは難しいので、型の練習の最中は常に行う事で、その感覚を馴染ませる効果があります。足裏を通して重心を地面の中まで沈める感覚や含胸抜背の状態は、力を出すのには向いているのですが、素早く動くのには向いていないからです。技を出す前には重心は丹田ではなく別の場所にあります。
ですから、ある程度太極拳の練習が進むと、型練習のうち、攻撃をする時に重心が深く沈んで、それ以外では身体は軽やかに浮いている感覚になります。これは流派や伝承者による違いもあるかと思いますが、私の習ったものは身体を軽くして素早く動き回り、一旦相手と接触した時は瞬時に身体を重く使うという戦略でした。その戦略の中で、具体的に自分の使う技を磨いていくのが個人の稽古になるわけです。
その為に、太極拳の鍛錬(補助的訓練)として小周天のような、気を縦に回す訓練や、一気に重心を落とす練習があります。太極拳の型だけを行って武術的な力をつけた人もいるようですが、それには多大な時間と才能や常に身近に良師がいる事が必要です。
一眼 二早足 三力 という教えもあるように、足の重要性は優先順位が高いものです。足と言えば、足関節から先の狭義の足と、股関節から先の広義の足(脚)があります。また、歩法も含まれます。ですから、足裏も当然大事なものです。足裏から見て、太極拳を再検討するのも、流派を問わず意義あるものかと思います。
Posted by 渡辺克敬(わたなべ かつゆき) at 00:04│Comments(0)
│太極拳、武術関連の話題