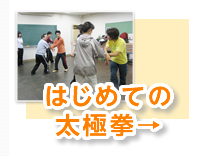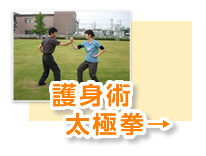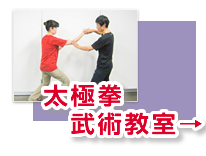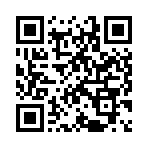2017年01月15日
双辺太極拳、正宗太極拳、などなど
↑ この方が陳冸嶺です。
私が行っている太極拳は「双辺(そうへん)太極拳」
と言います。
これは、南京中央国術館館長の陳泮嶺
(陳式太極拳の陳一族ではありません)が楊式太極拳をベースに、
陳式太極拳・呉式太極拳等を参考にして創出したものです。
特徴は、形意拳・八卦掌の要素が取り入れられている事です。
まず、立ち方が違います。多くの太極拳では脚を前後に開いた時に、
後ろ脚の膝を伸ばしますが、双辺太極拳は膝をかなり曲げています。
これはまさに形意拳の立ち方です。ですから足の出し方も、手と足が
同時に至る、という形意拳の出し方をしています。
双辺太極拳と正宗太極拳は、同様であるという話と、同系統であるが
微妙に違う、と言う様な内容がウィキペディアには見られます。
私の知っている両者は全くと言って良いほど別物です。
伝承者の違いや、同じ伝承者でもその年齢によって弟子に
教える内容が変わる事もあり、一様ではないようです。
日本の太極拳の黎明期、最初に太極拳を伝えたのは、
多くの人の知る所では、王樹金です。
その時点では、太極拳は陳泮嶺のオリジナルに近かったようです。
その後、王樹金はその太極拳に更なる工夫を加えていったようです。
王樹金は王向斉より站樁の教えを受けているとの事で、河野義勝氏の
DVDなど見ますと、その影響が感じられます。
陳泮嶺著の「太極拳教材」を見ると、ほぼ私の行っている太極拳です。
私の先生によれば、張逸仲が、ラン雀尾という技に左の掤を加えて、
呼吸がしにくくなったと言っていました。「太極拳教材」を見ますと、
確かに、私のやっている太極拳は一手増えています。
双辺太極拳の架式(型を行う時の大きさ)は、
高からず低からず、大きからず、小さからずの中架式です。
双辺太極拳の特徴は、やはり、形意拳の影響を受けている立ち方と
中架式ということでしょう。
正宗太極拳を名乗られている方は、「王樹金の太極拳」という場合が
多いようです。
王樹金の正宗太極拳を名乗っていても、面白い事に、架式に大きな差が
ある例もありました。どこで、なぜ変わったのだろうか?と考えると
興味が尽きません。
世代が変わると内容が変わる例はどの世界でもある事です。
それはそれで、多様化と適応という事で良いかもしれません。
しかし、オリジナルの良さもあるので、オリジナルはオリジナルで
別バージョンと並行して、そのまま伝承されていってほしいものです。
「太極拳真伝」 河野義勝著は入手可能です。DVDつきで良い内容です。
「太極拳教材」 陳泮嶺著は古本でも入手が困難です。
Posted by 渡辺克敬(わたなべ かつゆき) at 16:53│Comments(0)
│太極拳、武術関連の話題