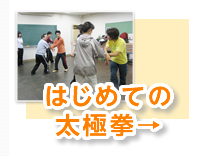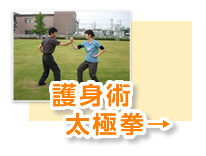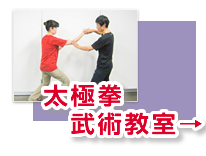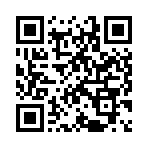2022年08月10日
含胸抜背の機能性
含胸抜背という言葉は、太極拳をやっている方なら
1度は聞いたことがあるかと思います。
流派や先生によって、重要度やその形・作り方には
多少の違いはあるかもしれません。
参考までにうちの流派では。
まず、胸含抜背は無理に作るものでは
ありません。適切に型稽古を行っていくと、
技が終わった時には、自動的にその姿勢になっている
というものです。
例えば、双按の場合。
前に出した左右掌で相手を打つ時に、示指先端を支点にして
手関節を回します。すると、余分な力が抜けていれば肩甲骨が
必要な動きを始めて、まさに含胸抜背という形になります。
無理にその形を作ろうとしても、力んで機能性の乏しい姿勢に
なるだけです。
上手くこの形を取る事ができると、上肢と身体の間に強い繋がりができます。
例えば、上の写真は鍛錬用の8kgの鉄棒です。
これを含胸抜背の状態であれば、手の上に載せてもさほど重さを感じません。
しかし、「今から鉄棒を載せるから」と言って手を出してもらうと、
もろに8kgの重さを腕で感じる事になります。
(上の写真が含胸抜背です。下の写真は普通の状態です。
下の写真を見ると、肘の辺りが力んでいるのが分かります。)
身体と上肢を上手く結びつけて、身体を機能的に使う方法の1つが
含胸抜背です。
Posted by 渡辺克敬(わたなべ かつゆき) at
16:55
│Comments(0)